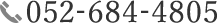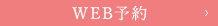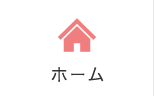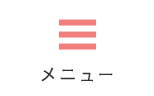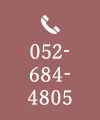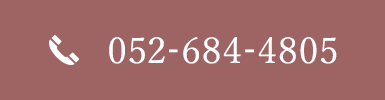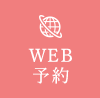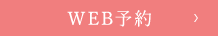便秘とは
 排便習慣はとても個人差が大きく、患者さんが便秘と認識していてもその内容はさまざまです。
排便習慣はとても個人差が大きく、患者さんが便秘と認識していてもその内容はさまざまです。
医学的には便秘とは「本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義されます。また「便秘症」とは便秘による症状が現れ、検査や治療を必要とする場合であり、その症状として排便回数減少による腹痛や腹部膨満感、硬便による排便困難や過度の怒責、便排出障害によるもの過度の怒責や残便感とそのための頻回便などがあります。
便秘の有病率
 慢性便秘症の有病率は報告により差がありますが、男性より女性に多くみられます。
慢性便秘症の有病率は報告により差がありますが、男性より女性に多くみられます。
とくに50歳以下の若年者では圧倒的に女性が多いですが、60歳以降は男女ともに加齢とともに増加し、70歳以上の高齢となると男女差がなくなります。
便秘が女性に多いのは、女性ホルモンの変動が腸管運動に強い影響を与えるからです。
しかし女性ホルモンの影響がなくなる更年期以降も加齢とともに便秘に悩まされる女性は増えていきます。加齢で便秘が増えるのは運動量や食事量など環境の変化が大きく関わっています。
男性では60代になると便秘が急増しますが、運動量や食事量の変化のほか、定年退職などによる環境の変化やストレスをきっかけにひどい慢性便秘になる人も少なくはありません。
いっぽうで、他の疾患で内服している薬の副作用で便秘になったり、ほかの病気があるために便秘になっている可能性もあるので注意が必要です。
40歳以上の人で便秘歴が短期の人はクリニックを受診し、がんや腸の炎症などの深刻な病気が隠れていないかを確認することが大切です。
大腸がん発生のリスク
便秘症が直接、大腸がん発生のリスクを増加させるかどうかについては不明です。
便秘の予防
「慢性便秘症 診療ガイドライン」にも適切な食事や運動、腹壁マッサージなどの生活習慣改善は慢性便秘症の症状改善に有効である、と記載されています。 生活習慣の改善は便秘の解消だけでなく、再発予防にも関係しとても大切です。
規則正しく3食きちんと食べる
3食、規則良く食べましょう。食事は1日のリズムに大きな影響を与えます。
規則正しい3度の食事は排便をスムーズにします。
とくに朝の食事は排便習慣を整えるためにとても重要です。
女性ではダイエット経験がある人や昼食摂取が少ない人に便秘が多いです。
食事のときはしっかり噛む
一口の咀嚼回数が30回以上の人には快便が多いと言われています。
食物繊維を摂る
食物繊維は便中に水分を蓄え、便の量を増加させてスムーズな排便を促します。
1日の必要摂取量が不足している人は食物繊維を多く含む食品を摂るようにしましょう。
1日あたりの推奨摂取量は成人男性で20g以上、成人女性で18g以上となっています。
しかし過剰な食物繊維の摂取は便秘を増悪させるので注意しましょう。
水分を十分に飲む
排便の習慣をつける
毎日朝食後に、便意の有無にかかわらずトイレに行くと、自然と便がもよおされるようになり規則的な排便の習慣が作られます。「便意があるのに排便しない」ということを繰り返していると、神経が麻痺して便意を感じなくなってしまいますので注意しましょう。
適度な運動をしましょう
ストレスを溜めない
慢性便秘症患者の6割に不安やうつなど精神的な問題を抱えているといわれています。
ストレスがたまると交感神経、副交感神経のバランスが崩れて腸の活動が低下します。
腸をマッサージする
腹部を温める
腹部をあたためると腸への血流が増加し、腸の動きが良くなり排便が促されます。